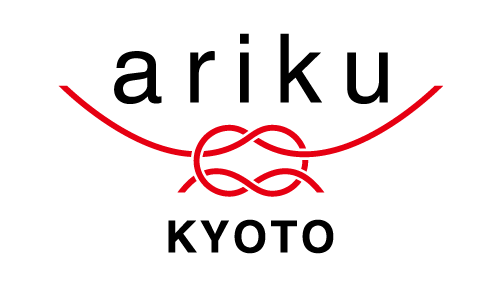2025/02/28 12:30
皆さんこんにちは。
前回に続き「京焼のスーパースター」4人をご紹介する第2弾!
幾分かわたしの独断が混ざっておりますが、素晴らしい作品と功績を残された方々ばかりです。
■奥田 穎川(おくだ えいせん)■
本名を頴川庸徳(1753-1811)といい、祖先は頴川郡(現中華人民共和国河南省)の出身。京都で代々質屋を営んだ。頴川も三十代まで家業を営むが作陶を志し,建仁寺内に開窯。
頴川といえば、京焼最初の磁器焼成大成者であり、京焼中興の祖。また、彼の門下から青木木米を初めとして、数々の名工を輩出し伝統的な京焼の全盛がもたらされたことは彼の大きな功績である。
作風は、呉須赤絵の模様を得意とし、古染付や交趾焼を真似て巧妙で雅かな磁器を制作した。
 呉須赤絵蓋物 『頴川といえば「呉須赤絵」が有名です』
呉須赤絵蓋物 『頴川といえば「呉須赤絵」が有名です』■青木 木米(あおき もくべい)■
祇園新地縄手白川橋畔のお茶屋「木屋」の長男として生まれる(1767-1833)。
中国の陶技書「陶説」を読んで作陶に進み、奥田頴川に入門した。文人陶工と称され、煎茶器を主体に作陶をおこない磁器製法の芸術性をさらに深めた。
青磁・白磁・金襴手・交趾・色絵・南蛮写しなどのやきものを制作している。なかでも急須はその冴えた作風で評価を得た。
.........................■□.........................
京焼は、土にこだわらず土地に拘束されない不思議な陶磁世界です。
市街地からは窯の煙が全く途絶え、仁清や乾山の窯跡からの発掘陶片などもごくわずか、東山一帯の古窯も確認できたものは少ないし、何だか夢のようでもあります。
ですが、そこが京焼の京焼たる所以なのかもしれませんね。
普段使いにもおもてなしにもお使いいただきたい、瑞鳥のお箸置きです♪