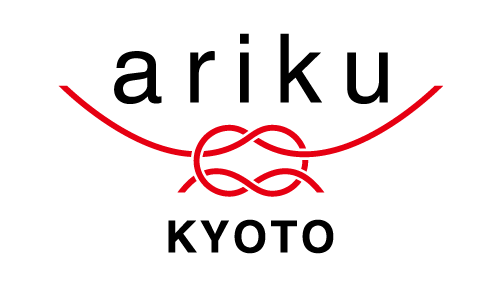2025/02/26 15:24
皆さまこんにちは。
少し寒さが落ち着いてきた頃、今度は花粉がやってきますね。
私はまだ花粉症になっていないのですが、いつも今年から発症するぞとの思いで、マスク、空気清浄機や乳酸菌の積極的な摂取を心がけております。
さて、今日も京焼のお話を少々。
皆さんは、現在の京焼職人が今でも尊敬と憧れを抱く4人の「京焼のスーパースター」をご存じでしょうか?
以下ご紹介していきたいと思います。
■野々村 仁清(ののむら にんせい)■
京焼色絵陶器の完成者。文献では、1648年に御室焼(仁清焼)として初めて登場する。
丹波国桑田郡野々村(京都府美山町)の出身で、元は丹波焼の陶工であった。粟田口を中心とする京焼がようやく盛んになり始めた頃、御室仁和寺前に窯を開いた。
仁清は、ろくろの名手として知られているが、京焼のスーパースターらしく釉法も多彩で、色絵の他、黄瀬戸・織部・唐津・信楽などの国内のやきものの手法をマスターし、天目・呉須・伊羅保・刷毛目などの中国陶磁、朝鮮陶磁の釉法にも精通していた。
その華麗で雅かな仁清の色絵陶器登場後、京焼の作風が大きく変化していった。特にその影響を強く受けて江戸初期から中期にかけて、東山山麓の各窯で「古清水」と呼ばれる色絵陶器が制作されることになる
 金彩おしどり『仁清に敬意と憧れを抱きつつ作陶しました』
金彩おしどり『仁清に敬意と憧れを抱きつつ作陶しました』■尾形 乾山(おがた けんざん)■
京都の呉服商雁金屋の三男、兄は有名な尾形光琳、曾祖母は数寄者本阿弥光悦の姉にあたる。光悦の孫にあたる空中斎光甫や楽一入に作陶の手ほどきを得たこともあり、1699年、仁清より陶法の伝授を受け、右京区鳴滝泉谷に開窯した。この窯場は市中の乾(西北)に位置することより乾山焼と名付けた。
乾山は、仁清の陶法を総合的に継承するとともに、王朝古典・漢画的主題を陶画に表現し、また琳派風のデザイン感覚に秀でたやきものを制作。生き生きとした筆使いや構図の巧みさ、色彩感覚の絶妙さに乾山の作品の特徴があり、意匠化された梅や菊など独自の文様が多くみられる。
そして、兄尾形光琳絵付のやきもの、乾山自筆詩歌のやきもの、欧風のやきものなど、独創的な作陶世界を京焼に展開した。
 乾山大皿/乾山写し 『現代京焼に数多くみられます』
乾山大皿/乾山写し 『現代京焼に数多くみられます』いかがでしょうか。
次回へ続きます!